腸の不調というと「食生活や生活習慣の乱れ」「運動不足」「ストレス」が原因と思われがちですが、じつは 筋肉や骨盤の状態 も大きく関わっています。
私が学んでいる日本腸セラピー協会では、姿勢や筋肉の状態が腸にとってとても大切だと伝えています。
特に「お尻の硬さ・冷え」「骨盤の歪みやねじれ」は、腸に悪影響を及ぼしやすいサイン。
お尻の代表的な筋肉として、大臀筋(だいでんきん) と 中臀筋(ちゅうでんきん) がありますが、「お尻を触ると冷たい」「お尻が硬い」と感じる方は要注意です!!
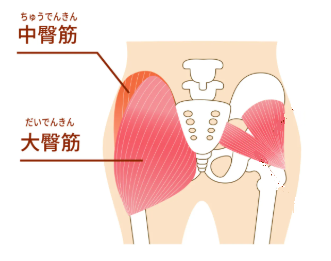
画像:ひなた整体院参照
お尻の筋肉はなぜ大切?
「大臀筋」は体の中で最も大きな筋肉で、骨盤から太ももにつながり、歩く・立ち上がるなど日常動作の土台を担っています。
また、片足で立つ際には、骨盤がぐらつかないように安定させてくれたりします。
「中殿筋」は大臀筋の奥にあるインナーマッスルで、骨盤の左右のバランスを取る筋肉で、体幹を安定させます。
片足立ちや歩行時には、骨盤を水平に保ってくれます。
日常生活であまり使わなかったり、悪い姿勢が続くことで、お尻の筋肉が弱くなって悪い状態で「コリ」となって固まってしまったり、血流が悪くなって冷えてしまいます。
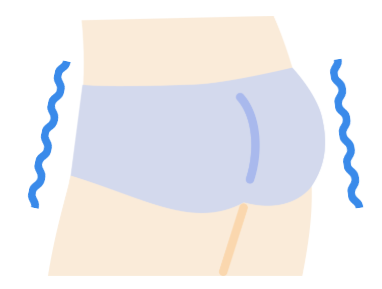
しなやかに働いていると骨盤は安定し、血流やリンパの流れもスムーズに。
腸に酸素や栄養がしっかり届き、排泄もスムーズになります。
でも、お尻の筋肉が硬くこわばると血管や神経を圧迫し、腸への血流が滞ります。
まるで“血流のダム”ができたように、血流をせき止めて巡りが悪くなることで、腸は冷え、働きが鈍りやすくなります。
さらに骨盤が固まって動きが悪くなり、姿勢の崩れも引き起こします。
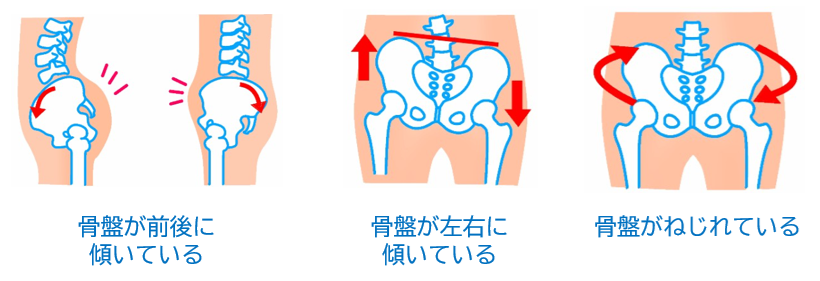
画像一部:美療鍼灸整骨院参照
こんな癖は要注意!
たとえば、無意識に「片足に体重をかけて立つ」ことはありませんか?
この姿勢はお尻の筋肉にアンバランスな負担をかけ、骨盤をゆがませる大きな原因になります。
長年の習慣で片側の筋肉ばかり硬くなり、反対側は弱くなるため、骨盤のねじれや傾きが固定化されやすいのです。

また、「座ったときに足を組む」癖も同じく骨盤の歪みを招きます。
片方のお尻に体重がかかるため血流が滞りやすく、骨盤のめじれや傾きに影響します。

骨盤の歪み・ねじれ・傾きが腸に与える悪影響とは?
骨盤は「腸のゆりかご」とも言える存在。
大切な臓器である腸をやさしく包み込み、守り、適切な状態に保ってくれています。
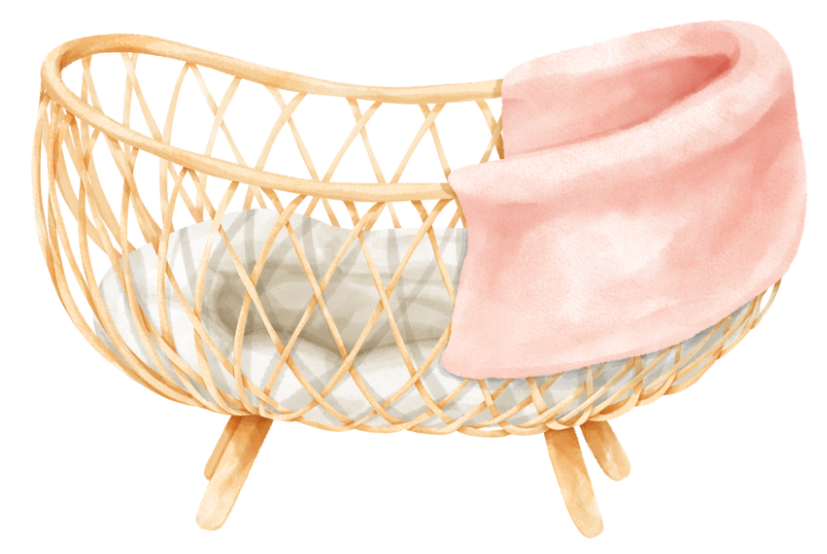
でも、骨盤の状態が悪くなると、腸に次のような悪影響が及びます。
1.腸のスペースが狭くなる
ねじれや傾きで内臓が圧迫され、本来の位置を保たれないことで、腸がのびのびと動けなくなります。
2.血流やリンパの流れが停滞
血管が圧迫され、腸への血流不足・冷えを招きます。
3.腸が下垂する(下がる)
骨盤が後傾すると腸が下に落ち込み、便秘やぽっこりお腹の原因に。
4.自律神経の乱れ
骨盤の歪みは背骨にも影響し、背骨を通っている自律神経が乱れやすくなります。
結果として腸の動きにもブレーキがかかります。
他にも、腰痛、むくみ、冷えなどなど、不調の連鎖につながることも・・・
お尻が垂れることにも影響します。

改善のポイント
1.お尻を温める
湯船にしっかり浸かる、腹巻やカイロでお腹を温めて血流を回復。腸の冷えも改善します。
2.お尻の筋肉をゆるめる
サロンではお尻の筋肉をゆるめるオイルマッサージを行っていますが、簡単にできるストレッチの仕方をお伝えしていきます。
3.姿勢のクセを意識する
座っているときに足を組まない、片足重心で立たない。
最初は意識的に「両足で均等に立つ・座る」を習慣化することが大切です。
4.階段を使う
なるべく階段を使うようにし、血流と骨盤の安定を取り戻しましょう。
まとめ
お尻の筋肉は、骨盤と血流を支える大切な筋肉。
お尻が硬い・冷えていると血流が滞り、腸の働きに悪影響を及ぼします。
さらに、足を組むクセや片足立ちの習慣は骨盤の歪みやねじれを生み、腸が働きにくい状態となり、下垂や便秘の原因にもなります。
腸活というとお腹ばかりに意識が向きがちですが、じつは「お尻と骨盤のケア」は腸を元気にする近道。
お尻を温め、ゆるめ、正しい姿勢を意識することで、腸はもっと快適に働いてくれます。
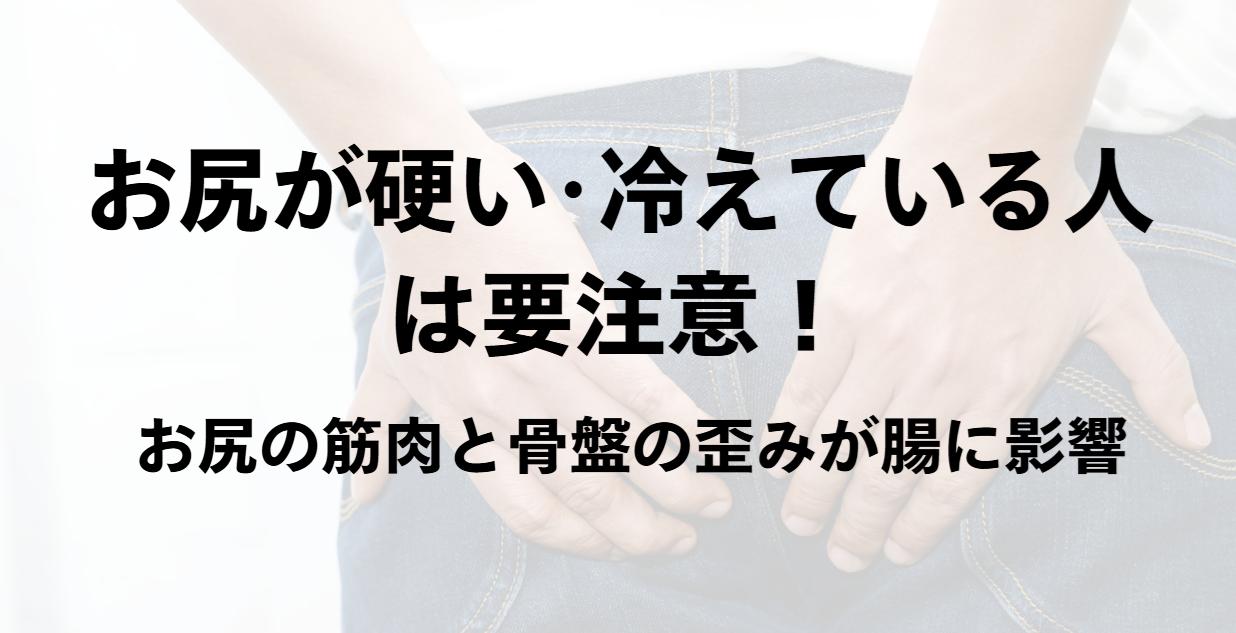
コメント